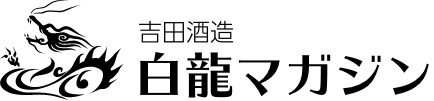へしこの由来
へしこは、福井の伝統的発酵食品で保存食です。
塩や魚介類、海藻類といった新鮮な海の幸と米に恵まれている福井県では、
魚と塩と米糠を使った発酵食品が生まれました。
それが、鯖や鰯で作る「へしこ」です。米糠(こんか)漬けとも呼ばれています。
魚類の糠漬けの起源は古く、文献に依れば鎌倉時代より行われていたようです。
魚の糠漬けにはいろいろな魚が使われます。
鯖、鰯、いか、はたはた、ふぐなどを使って作りますが、
特に鯖や鰯は代表的なもので、この糠漬けのことを「へしこ」と呼びます。
この呼び名はヒシオ(干潮)から変化したと言われています。
ヒシオというのは魚を塩漬けにして2、3日経つと浮き出してくる魚の体内の水分(塩汁)のことをいうのですが、
このヒシオがなまって「へしこ」と呼ばれるようになったのだということです。
また、漁師ことばに鯖を木樽に漬け込むことを「へし込む」といい
それがなまって「へしこ」となったとも言われています。
「へしこ」は、新鮮な鯖を塩漬けにし、いったん取り出してからぬかに漬け、
本漬けにして一年から二年の長期にわたって漬け込み、熟成したものです。
雪深い福井県。
長い冬の間の貴重なタンパク源でもありました。
今は、酒の肴として、あぶって食べるだけでなく、色々な料理方法が考えられています。
へしこTVの中でも、色々な料理方法をご紹介します。
へしこは、なぜ、旨い?
へしこの旨みは原料となるサバの脂と米ヌカとの出会いから始まる。
脂ののったサバと、渓谷の清冽な湧き水で育った地元米のヌカを使うことで、
滋味豊かなへしこができあがる。
晩秋にサバを割って内臓をきれいに取り除き、腹に塩を詰める作業は、
冷たい寒いを通り越して「痛い」。
なぜ、この時期に漬けるのか??
油ののった鯖を使いたいから。
また、はじめの塩漬けの段階で発酵が進んで酸っぱくなってしまうのを防ぐためだ。
だから、厳寒の寒さの中に、
丸々と厚みのあるサバを1本1本傷つけないように丁寧に、
しかも素早く処理していく。
それが終わると表面にも塩を振り、
漬け込み作業に入る。
これが「塩押し」と呼ばれる第一段階の塩漬けである。
「塩押し」は、大体1週間から2週間。
その間にサバからヒシオがにじみでて、
本漬けのときの味つけがなじみやすくなり、
保存性も高まる。
水が浮いたら一度全て取り出し、
塩を落として、みりん・醤油などで下味をつける。
それからヌカを塗るようにまぶし、
他の調味料と共に再び貯蔵樽に重ね入れる(本漬け)。
最後に重石をしたら、
夏の土用をはさんで1年から2年寝かせておく。
へしこづくりに携わる人たちは一様に
「土用を越さないとへしこにならない」と言う。
夏の土用の暑さを経て、
はじめてサバとヌカの旨みが溶け合い、サバはへしこに変わる。
へしこは、福井の伝統的発酵食品で、先人の知恵で、
人を思う愛がこもっていると信じております。
へしこは、酒の肴として最高!なので
白龍でも販売しております。
電話 0776-64-2015